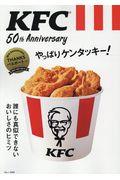![]()
©SHINCHOSHA
〈“稀代のスーパースター”三島由紀夫と、彼を敵対視する“反逆のエリート”東大全共闘。禁断のスクープ映像が、ついに解禁される――〉
50年前の1969年5月13日に行なわれた、“伝説の討論会”。その模様を記録した貴重な映像が、13人の“証言者”へのインタビューとともに、一本のドキュメンタリー映画になりました。
「東大駒場キャンパス900番教室に集まった者の一人として討論会を“体感”できるよう、大きなスクリーンで見てもらいたい」そんなプロデューサー陣の思いから映画化が企画され、白羽の矢が立ったのが豊島圭介監督でした。
東大教養学部出身で、900番教室のある駒場キャンパスで学生時代を過ごした豊島監督。今作「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」にどのように臨んだのか、お話を伺いました。
![]()
豊島圭介(とよしま けいすけ)
1971年、静岡県浜松市生まれ。東京大学在学中の「ぴあフィルムフェスティバル94」入選を機に映画監督を目指す。卒業後、ロサンゼルスに留学。AFI監督コースを卒業。帰国後、篠原哲雄監督などの脚本家を経て2003年に「怪談新耳袋」(BS-TBS)で監督デビュー。以降、映画からテレビドラマ、ホラーから恋愛作品まであらゆるジャンルを縦横無尽に手掛ける。
映画は「裁判長!ここは懲役4年でどうすか」「ソフトボーイ」(ともに2010)、「花宵道中」(2014)、「ヒーローマニア-生活-」(2016)、「森山中教習所」(2016)など。テレビドラマは「ホリック~xxxHOLiC~」(2013)、「黒い十人の女」(2016)、「徳山大五郎を誰が殺したか?」(2016)、「I”s(アイズ)」(2018)、「ラッパーに噛まれたらラッパーになるドラマ」(2019)、「特捜9」(2019)などがある。
割腹自殺の1年前 三島由紀夫vs東大全共闘、伝説の討論会
――「三島は“古臭い知性”だ」「三島を論破し、舞台の上で切腹させてやる」と盛り上がる1,000人の学生たちと、敵地へ単身乗り込んでいった三島由紀夫。何が起きてもおかしくないとハラハラする気持ちがあったのですが、いざ映画が始まると、中盤あたりから900番教室が和やかともいえる雰囲気になっていくんですよね。三島由紀夫も、この討論会を「大変愉快な経験であった」と書き残しています。
「三島由紀夫vs東大全共闘」の製作にあたって、もちろん大筋の構想は立てていたんですが、自分の立てた仮説に誘導するような作り方はしないと決めていました。
討論会の映像を見て、当時のことを調べ、13人の“証言者”の方々にインタビューする。そんなふうにして製作を進めていくなかで、浮かび上がってきたのが「言葉と敬意と熱がいかに重要か」ということでした。もはや「それしか浮かび上がってこなかった」と言っていいくらい。
―― 討論会ではあるんですが、だんだん“対話”の側面が強くなっていったように感じました。だから「大変愉快」だったのだろうなと。
それが「敬意」と「熱」なんでしょうね。
いま、コミュニケーションの場なのにコミュニケーション不全に陥っている状況があちこちで起きていると思うんです。「いいね」を押して賛同を示したり、RTしたりはするけれど、その議論に自らを投じることはなかなかしない。その場に身を置く者も、意見ではなく罵詈雑言の言いたい放題……そんな光景をよく見ませんか?
今回、構成台本を作るにあたって“仮想敵”のような形で置いたのは「SNSで匿名で行なわれる議論」でした。自分が何者であるかを伏せて、言いたいことだけ相手にぶつける。それは、900番教室で行なわれたのと同じ“議論”なんだろうか? 背景や立場の異なる生身の人間が、汗や息、体温をリアルに感じる距離で言葉を交わすことに、いったいどんな価値があるのだろうか。
そんなふうに考えたとき、「日本の現状に対するカウンターパンチとして、この人たちは非常に意味のあることをしていたんだ」と思ったんです。なので、この討論を今の時代にどうフィードバックできるか、それをずっと考えていました。
当時の彼らは、たとえば高倉健さんの任侠映画に触発されて、その昂ぶりを自分たちの学生運動にフィードバックしていたわけですよね。今作はドキュメンタリーですが、それと同じように、観終わった後になんだか心の中が燃えているような、高揚感とともに劇場から出てきてもらえるような一本を目指しました。
![]()
製作期間の半分以上を“仕込み”に費やした
―― 豊島監督にとっては、15年以上のキャリアにおいて初のドキュメンタリー作品ですね。
初めて手がけるドキュメンタリーが三島由紀夫とは、とんでもない仕事を引き受けてしまったなと思いました(笑)。
映像自体はすでにご覧になったことがある方も多いと思うのですが、プロデューサーの皆さんの間で「映画館で観られるようにしよう」という動きになりお話をいただきました。その後、映像の原盤であるフィルムが見つかったことで、フィルムのデジタル・リマスターが行なわれ、(もともと保管されていた)ビデオテープの4倍の解像度で観られるようになったんです。
僕も部分的には映像を見たことがありましたが、三島由紀夫についての知識や理解もごく一般的なもので、政治や学生運動をはじめ当時の情勢もくわしくは知らない。そんななかで映画化を前提としてフィルムを見たので、「どこからどう手をつければいいだろう」と最初は途方に暮れました。
当時の青年たちと僕はボキャブラリーを共有していないし、文化的な背景も違います。そのときの心情も、想像することしかできない。恋愛のいざこざならある程度は理解できても、討論会の内容は政治や芸術に関するものが多くて、なおさら難解でしたから。
![]()
―― 2018年初頭に映画化の企画が動き出し、監督はその翌年から製作に入ったと伺いました。「最初は途方に暮れた」とのことでしたが、その後どのように進めていったのでしょうか。
製作期間の半分ほどは“仕込み”に費やしました。構成台本を作るのに一番時間がかかりましたね。知らないことやわからないことがたくさんあって、挙げればきりがない。調べながら自分なりに“答え”だと思うものをメモして、それがだんだんパズルのように埋まっていって、「これでひとまず、インタビューができるくらいにはなったかな」という状態になるまでに半年くらいかかったと思います。
初めてやってみて、ドキュメンタリーって“総力戦”だなと思いました。大筋を考えて構成台本を作ったら、「楯の会」や「全共闘」とカテゴリーごとに担当を立て、関係者の方や資料の持ち主を調べて交渉していく。これはチームだからこそできることであって、一人ではとてもできないです。
たとえるなら、絨毯爆撃のようでしたね。短期間で映画を完成させられたのは、そのおかげです。
インタビューも初めてだったので、「いざお会いした時に面と向かって何を質問するか」という難しさもありました。最初のインタビューは橋爪大三郎先生だったんですが、橋爪先生の全共闘にまつわる発言を拾い出し、質問を考えて、「これは事前にお渡しする書類にも記載していい“見せる質問”、こっちは“隠しておく質問”」と作戦を立てていったんです。
―― フィクションの物語と違って、脚本はないわけですからね。
ただ最初にお話ししたように、頭の中にある“構想上の答え”に誘導するようなインタビューだけはしないと、それだけは肝に銘じていました。
―― インタビュイーの皆さんも、その点をかなり警戒していらっしゃったのではと思います。
そうですね。特に「楯の会」の方も「三島先生のことをマスコミがいいように書くんじゃないかと、それだけが心配です」とおっしゃっていました。三島由紀夫という、尊敬する存在であり、仲間でもある人物が自死をもって生涯を閉じたわけですから。
尊敬する人の死を軽々しく語るものではないし、絶対に誤解されたくない。それでもインタビューを受けてくださったのは、やはり三島の死から50年経ったということが大きいと思います。
50年の間に当時の仲間たちは高齢になり、そのなかには大病を患う方や、亡くなる方も増えてきた。ちょうど50年の節目ということもあり、「そろそろ自分もいつ死ぬかわからないから残そうと思った」と応じてくださったんです。
―― インタビューで、ほかに印象的だったことはありますか? 私は、芥正彦さん(※)の鋭い目が今も忘れられません。映画を観ているときも「今ちゃんと自分の頭で考えているか?」「傍観者でいるつもりじゃないだろうな」と言われているようで、体がぎゅっとなりました。
※“全共闘随一の論客”といわれた存在。東大在学中の1967年に前衛劇団を主宰し、現在は劇団ホモフィクタスを主宰。演出・劇作・舞踏・アートパフォーマーなど、74歳を迎えた今も多岐にわたり活動している。
普段もインタビューのお仕事をされているから、緊張感がよけいリアルに伝わってきたんでしょうね(笑)。実際にお会いしてインタビューをしたとき、芥さんはあの頃から今もまだ、議論を続けているんだと感じました。
先ほどの「誤解されないように」という話でいうと、平野啓一郎さんにお話を伺ったときのことが印象的でした。お聞きしたいことをあらかじめお渡ししていたんですが、当日、さあ質問を始めようとしたら「質問の内容を読んで僕なりにまとめてきたので、まずは一度聞いていただけますか?」とおっしゃったんです。
平野さんのなかにも“三島由紀夫”という存在が強くあって、部分的に答えたのではそれが歪むかもしれない。全体像を逃すことのないようにと、用意してくださったんだろうなと思いました。
![]()
三島由紀夫とは、どんな存在だったのか
―― 最後の質問になるのですが、今もなお三島由紀夫に人々が関心を寄せる理由は、どこにあると思いますか? 今作で“三島由紀夫”という人物に向かい合ってみて、どんなことを感じたか教えていただきたいです。
椎根和さん(※雑誌編集者。「平凡パンチ」で三島を担当し、ただ一人の剣道の弟子でもあった)がおっしゃっていたんですが、三島由紀夫と会話をしていると、自分が何倍も頭が良くなったような気持ちになるんですって。いろんなことを次から次へと惜しみなく教えてくれるし、「こんな高度な会話に自分が参加している」という高揚感がある。
それって、三島由紀夫が誰に対しても、ものすごく真摯に接していたということじゃないかと思うんです。楯の会の仲間たちにも、全共闘の学生たちにも、編集者にも、作品の読者たちにも。たった45年の限られた人生で、あれだけ大勢の人間に本気で接することができるって、ほんとうに稀有な才能だと思います。
![]()
それと同時に、あまりに多面的であることが「三島由紀夫とは何者だったのか?」という謎を深めているようにも思いました。
ノーベル文学賞の候補にも挙がった世界的な文豪であり、俳優であり、映画監督であり、舞台演出家でもあり、政治活動家でもあった。いろんな顔があってその全部に本気だったから、その生涯で何を成そうとしたのか、なぜ自決を選んだのかが、いまだに論じられたりしているわけです。今回「三島由紀夫vs東大全共闘」を撮って、そういう魅力が人々の心をとらえているんじゃないかなと思いました。
僕たちスタッフは、取材のたびに刺激を受け、高揚してそこから帰ってきました。映画を観た直後のエネルギーは何分ともたないかもしれませんが、この気持ちができるだけ長持ちするように生きていきたいなと思っています。それも、本作を撮って得たことの一つです。
![]()
©SHINCHOSHA
今回筆者が「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」を観て、豊島監督にお話を伺って感じたのは、三島由紀夫や、彼に対峙した芥正彦氏の圧倒的な“個としての強さ”でした。
自分は何者でもない。自分が何をしたところで、世界は変わらない。
そんなふうに思っていても(この姿勢を内田樹氏は「非政治的」と表現していました)、「何者にもなりたくない」という人は多くないのではないだろうか。だから、モラトリアムの時期に悩んだり、匿名でやり方がひねくれていても、“自分がここにいる”ことを発信したくなったりするのではないだろうか。
だからこそ、(思想に共鳴するかは別として)三島由紀夫のような「政治的な」存在は、どんな時代にあっても人々が無視できないのではないか。
そんなことを感じました。
「三島由紀夫と東大全共闘の討論会は、人々を一気に“あの頃”へ引き戻す力がある」―― 本作について、豊島監督はそんなコメントも寄せています。
“あの頃”を知らない私は、自分と同じような人たちに、そんなにまで吸引力のある“あの頃”とは何だったのかを、ぜひ体感してみてほしいなと思います。
- 東大全共闘1968ー1969
- 著者:渡辺眸
- 発売日:2018年04月
- 発行所:KADOKAWA
- 価格:1,496円(税込)
- ISBNコード:9784044003883
映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」
〈STORY〉1968年に大学の不正運営などに反対した学生が団結して始まった全国的な学生運動、過激さを増していた東大全共闘に、言葉とペンを武器にする文学者・三島由紀夫は単身で乗り込んだ―。伝説となった「三島由紀夫VS東大全共闘」の記録を高精細映像にリストアし、当時の関係者や現代の文学者・ジャーナリストなどの識者他、三島由紀夫についての「生きた」証言を集め、約50年の時を経た今、ついにその全貌が明らかになる。
三島由紀夫
芥正彦(東大全共闘) 木村修(東大全共闘) 橋爪大三郎(東大全共闘)
篠原裕(楯の会1期生) 宮澤章友(楯の会1期生) 原昭弘(楯の会1期生)
椎根和(平凡パンチ編集者) 清水寛(新潮社カメラマン) 小川邦雄(TBSテレビ記者)※肩書は当時
平野啓一郎 内田樹 小熊英二 瀬戸内寂聴
ナレーター:東出昌大
監督:豊島圭介
企画プロデュース:平野隆
プロデューサー:竹内明 刀根鉄太
音楽:遠藤浩二
製作:映画「三島由紀夫vs東大全共闘」製作委員会
制作プロダクション:ツインズジャパン
配給:ギャガ
3月20日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国公開
gaga.ne.jp/mishimatodai/
©2020映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会



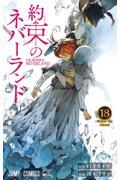
















 (@midsommarjp)
(@midsommarjp)