![]()
2019年9月、いしいしんじさんの3年ぶりの小説集『マリアさま』が、リトル・モアより刊行されました。
2000年から2018年に書き溜められた短編・掌編から、「新生・再生」をテーマに選りすぐった27篇を収録した『マリアさま』。いしいさんへのインタビューは、“これまでの約20年”を振り返ることから始まりました。
![]()
いしいしんじ
1966年、大阪生まれ。京都大学文学部卒業。94年『アムステルダムの犬』でデビュー。2003年『麦ふみクーツェ』で坪田譲治文学賞、12年『ある一日』で織田作之助賞、16年『悪声』で河合隼雄物語賞を受賞。そのほか『ぶらんこ乗り』『ポーの話』『四とそれ以上の国』『海と山のピアノ』など著書多数。
趣味はレコード、蓄音機、歌舞伎、茶道、落語。
- マリアさま
- 著者:いしいしんじ
- 発売日:2019年09月
- 発行所:リトル・モア
- 価格:1,650円(税込)
- ISBNコード:9784898155103
――『マリアさま』というタイトルはどのようにして生まれたんですか?
編集担当の熊谷さんが、最初に「マリアさま」と言ったんです。
装画の話を聞いていた時、熊谷さんが「装画は有山達也さんにお願いしようと思います」「有山さんは最近、長崎へ行って教会のステンドグラスを写したりしているそうです。今回の表紙も、ステンドグラスに光が差し込んでいる時のような、マリアさまが降りてきているような感じがいいと思うんです」とおっしゃって。
その時に「あ、マリアさまって言ったね」と。「『マリアさま』って、熊谷さんにとって普段から言う言葉じゃないでしょう。つまり言葉が先に来たってことやから、そのまま本の名前にしたらいいと思う」ということで、この本のタイトルは『マリアさま』になりました。熊谷さんにふっと舞い降りてきたものを、2人で拾った感じです。
――『マリアさま』は、これまでの約20年間が詰まった一冊でもあります。2000年というと、『ぶらんこ乗り』が刊行された年なんですよね。収録されている「子規と東京ドームに行った話」が、この年に書かれたものです。
『ぶらんこ乗り』を書き終わったときに書いたお話ですね。「野球小僧」という野球雑誌に書いたもので、その雑誌はのちに「野球太郎」という名前になるんですけど、それを中心となって作っていた高橋さんと親しくて、「野球について書いてくれないか」と話をいただいたんです。
2000年の野球だから、オバンドーとかが出てくるでしょ(笑)。書いた当時も「現代に明治の人が現れる」っていうギャップがあったわけですけど、それからさらに今回「約20年経った今読む」という新しい時間軸が加わっている。それもまた面白いなあと思いました。
今振り返ってみるとこの話は、“書くよろこび”が素直に出ていますね。そういうお話も入れられて、よかったです。
―― いしいさん、普段はご自分の書いた小説を読み返しますか?
読み返さないです。今回『マリアさま』という一冊の本に編むことになって、そのゲラで初めて読み返しました。
読んでみて、率直に「変わってないな」と思いましたね。(写真家の)鬼海弘雄さんが、ありがたいことに本が出るたびに感想をくださるんですけど、鬼海さんも『マリアさま』を読んで「変わってないな」と思ったんですって。最初に「犬のたましい」というお話が入ってるでしょう。それを読んで「いしいしんじはすごい境地に到達したのでは」と感じ入ったのもつかのま、巻末の初出を見て「10年以上も前じゃないか!」ってずっこけたそうで(笑)。
自分でも、今書いているものを含め、これまで書いたどの作品も、内容やテイストは違うんですけど、小説の中に入って読んでみると全然変わっていないんです。安心しましたね。
『たいふう』との再会、そして“新生”
―― 変わっていないことに「安心した」。
『ぶらんこ乗り』を書いたから『トリツカレ男』を書いた、『トリツカレ男』を書いたから『麦ふみクーツェ』を書いた……というふうに、書いた順に作品がひとつの線で繋がっていて、今回読み返した27篇も、背景にちゃんと同じものが響いていたんです。その原点に、4歳半の時に書いた『たいふう』という小説があります。
僕は28歳で小説家としてデビューした後、33歳の時にパンクして、身体と精神がおかしくなってしまったんです。それで療養のために東京から大阪の実家に戻ったんですが、部屋でごろごろしていたある時「俺ここで、いつも何してたんやっけ」と思って、母に聞いてみました。
そうしたら「あんた、いっつもそこでお話ばっかりずっと書いてたやん」「4歳から6歳まで幼児生活団(大阪友の会幼児生活団)行ってたやろ。3年間で20か30は書いてたと思うで」と。「取っといて、どんなんやったか見たかったなあ」って言うたら、2階のつづらに全部入れてあると言うので、2階へ上がって、自分のぶんのつづらの蓋を取ったんです。
そこには、画用紙を切って、ホッチキスやセロハンテープで束ねた手製の本が茶封筒に入っていました。一番上にあったのが、最初に書いた『たいふう』です。それくらいの年頃なら絵を描く子が多いんでしょうけど、それは「小説」でした。
つづらを開けた時、茶封筒が「お前、やっと来たな」「やっとここに戻ってきたか」と言ったのを、はっきり感じたことを今も覚えています。
おーい、たいふうがくるぞー。みなとのひとがいいました。ものすごいたいふうがくるのです。おきに、ちかづいて、いるのです。ぎょそんのみんなはふねをくいにしばり、やねをしゅうぜんし、とぐちやかべにいたをうちつけました。
ところが、ひねくれおとこがひとり、いいました。
「へ、おれはたいふうなんてこわくないねえ」
そしてひとりでふねをだし、おきあいにでていってしまったのです。
そのよる、たいふうはしんろをかえ、ぎょそんをまっしぐらにちょくげきしました。ふねもやねもいえも、ひとびともいぬもぜんぶ、そのよるのうちに、たいふうにふきとばされてしまいました。
つぎのあさ、ひねくれおとこがもどってきました。
そこにはなんにも、ありませんでした。
そのひから、ひねくれおとこは、ねるのも、はみがきも、あさごはんをたべるのもばんごはんをたべるのも、ぜんぶひとりでやらなくちゃいけませんでした。ひねくれおとこはしょっちゅうそらをみて、こんなふうにおもうのです。
こんどたいふうがきたら、きっとおれも、ふきとばされてやろう。(「たいふう」より)
『たいふう』を読んで、びっくりしました。なんやこれ、と思いました。4歳半のいしいしんじが、勇気をもって「生きること」「死ぬこと」に立ち向かって、怖いながらも何かを残そうしていたのがわかる。
その時、「今まで書いてきたものは、全部どうしようもないクソやったんや」と思いました。時評もエッセイも、旅行記も書けるし、インタビューや対談の記事も書く。物語も書いた。リクエストをくれたから、渡す。期待以上のものが書けていたら、喜んでもらえる。でも、自分の中にある“大切なもの”を渡すようなことは一度もなかった。それまでの33年の人生で値打ちのあるものは、4歳半で書いた『たいふう』しかなかったんだと。
しんどかったですね。でも、だんだん「これだけは世界中の誰に見せても恥ずかしくない」「ほかがクソやったとしても、これだけはできたんや」と思い直すようになりました。
それで「4歳半の俺がやったことをそのまま、30年間に身につけた言葉でやってみよう」と、『ぶらんこ乗り』を書いたんです。いうなれば僕は、『たいふう』に再会して、『ぶらんこ乗り』を書いたことで“新生”したんやと思います。
- ぶらんこ乗り
- 著者:いしいしんじ
- 発売日:2004年08月
- 発行所:新潮社
- 価格:572円(税込)
- ISBNコード:9784101069210
いしいしんじが描く死の「風通しのよさ」
――『たいふう』にも『ぶらんこ乗り』にも、誰かの死と、いま生きている人が描かれています。『ぶらんこ乗り』を初めて読んだ時は、その寂しさの感じがとても新鮮でした。
『たいふう』を書いた4歳~5歳頃から、「自分が死んだら」「お父さんやお母さんが死んだら」ということをよく考えていました。「俺が死んだら、皆めっちゃ悲しむやろうけど、ご飯は食べるし、3日くらい経ったら笑うようになって、1週間経ったらテレビで漫才見て笑ったりするはずや」「そこに俺がいなくても、皆の生活は進んでいくんや」って。
『ぶらんこ乗り』にも、ぶらんこで“あっち”へ行ったり、“こっち”へ戻ってきたり……という要素がある。日常生活でもね、まだ運転免許証を持っていた頃、高速道路を走っていてカーブに差しかかるたびに「このまままっすぐ行ったら死ぬな」「対向車線にちょっとハンドル切ったら死ぬな」って思いながら運転していました。
死にたいわけではなくて、それくらい僕は「死」というものに対して敏感で、水面下すぐのところに常に「死」のイメージがあるんです。それが、小説を書くときの源にもなっています。
でもね、「死」を書いていても、暗くはないでしょう。『マリアさま』にもたくさんの人の「死」が描かれていますけど、これも暗くないですよね。自分でも不思議ですけど、それって、僕が“向こう側”の気配をいつも身近に感じていて、「亡くなった人たちは“向こう側”に行ってしまったけれども、ちゃんとそこにいて、時々サインをくれたりする」と信じているからじゃないかなと思うんです。
僕は『ある一日』で、人が生まれる場面を書きました。「出産のお話ですね」とよく言われるんですけど、実はこのお話は、出産じゃなくて「誕生」の話です。
出産は女性しかできないけれど、誕生は誰もが経験しているでしょう。僕はその「誕生」を、自分の子どもが生まれる場面に立ち会って、もう一度感じたんです。看護師さんに子どもを渡された時、体がぶるぶるぶるって震えて「生まれた時の記憶はないけど、体が覚えてるんや。それで今震えてるんや」って思ったんですね。
もっと言うと、“向こう側”から生まれてきて、死ぬと“向こう側”へ行く、自分はその間にいるんだなと感じたんです。
たぶん、そういうふうに「死」を丁寧に、大事なものとして扱ってるから暗くならないんです。風通しがいい、ともいえるかもしれないですね。
僕はいろんなところを旅したし、引っ越しも何度もしましたけど、引っ越し先はどこにしたところで同じ地球の上なので、さして重要じゃないんです。僕はどこに住んだとしても、そこに暮らして自分にあったこと、自分の中から生まれてくるものを書きます。
重要な引っ越しは、何もないところからすごいエネルギーでこっち側へやってきた時と、あちら側へ戻る時。この2回だけです。
あらためて読み返した時、そういう点で、いつ書いたどの作品も同じだった。それが「変わらなくてよかった」ということです。
- ある一日
- 著者:いしいしんじ
- 発売日:2014年08月
- 発行所:新潮社
- 価格:440円(税込)
- ISBNコード:9784101069326
松本でのこと
―― いしいさんは大阪生まれで、その後京都、東京、三崎、松本と移り住んだ後、現在京都にいらっしゃるんですよね。実は編集部に、松本にお住まいだった頃の取材記事がありまして……。(「新刊展望」2005年5月号 創作の現場より)
![]()
柿の木が裸だから、冬ですかね。松本は、寒さが強烈だったなあ。一番ひどい時なんて、マイナス18度くらいまで下がるんですよ。
毎朝5時に起きて書いていたんですが、朝お風呂場の扉を開けると、前の夜の蒸気がそのまま凍って、タライやら石鹸箱やらが、じゅんさいみたいに一枚の氷でつながっているんです。家の中につららができるくらいですからねえ。
―― あ、じゃあここに書いてある「三崎にいたときはいろいろ出歩いていたのが、松本に越したらずっと家にいてほとんどしゃべらない生活になった」というのは……。
そういう気候だからですね(笑)。おもしろいな、そんなこと言うてたんや。ああ、草地に狐の死体が横たわっていた話もしていますね。松本は、日常のすぐそこに“死”があったんですよねえ。
いろんなことがありましたね、松本では。
園子さんと入籍して松本へ越して、その翌年にすぐ赤ちゃんができました。でも5か月で亡くなってしまった。僕は松本へ越してすぐ、園子さんがまだ妊娠もしていなかった頃から『みずうみ』という小説を書いていて、それはちょうど第一章が書き終わった頃でした。
自分自身ではまったく意識していなかったけど、月に一度水が溢れて引いていく“みずうみ”は、どう考えても月経周期をあらわしている。そして第一章の最後が、その後の死産を予感しているとしか思えないんです。
それから、二人で暖かいところへ行こうということでキューバへ行って、帰ってきてから第二章にとりかかりました。タクシー運転手の話を書いているうちに、だんだん「第三章では“慎二”が実名で出てくる」ということがはっきり浮かび上がってきて、「ああ、俺は自分たちのことを、あの場面を書くのか」と。
初めて「小説を書くのが怖い」と思いました。書くことしかできないから書くんですけれど、あの時、小説に対する畏れが生まれました。
- みずうみ
- 著者:いしいしんじ
- 発売日:2010年11月
- 発行所:河出書房新社
- 価格:616円(税込)
- ISBNコード:9784309410494
それから松本では、猿田さんという大親友との出会いもありました。この家を世話してくれた不動産屋さんで、園子さんの機織りの師匠のお友達なんですけど。
最初に猿田さんのところへ挨拶に行ったとき、傍らにサミュエル・ベケット全集と、大正時代の分厚い聖書が置いてあったんです。「本、お好きなんですね」とおしゃべりしていたら、猿田さんは、もともとお父さんが不動産屋を営んでいて、猿田さん自身は大学を卒業した後料理の道に進みたかったらしいんですが、お父さんが体調を崩されたので、松本へ戻ってきて家業を継いだのだという話をしてくれた。それと、一家皆さんキリスト教徒で、お兄さんは牧師をやっているということも。
それからは、僕が三崎に住んでいた頃から付き合いのある「まるいち魚店」で猿田さんが鯖を仕入れて、鯖寿司を振る舞ってくれたり、安曇野でとれたとびきりのりんごでアップルパイを作って持ってきてくれたり……。ほんまに、親戚のおじさんみたいな素晴らしい人でね。すぐに親しくなりました。
でも、ある日三崎へ行って小説を書いていた時、園子さんから「大変なの、猿田さんが交通事故に遭ったって」と電話がかかってきたんです。「夜に外を歩いていて、はねられてしまったらしいの。車のほうは逃げてしまったそうだけど……」と。僕は「猿田さん、うっかりしてるなあ」と言ったんですけど、園子さんがそれきり黙ってしまったんです。
「どうしたん」と聞いたら、病院へ運ばれたものの、意識が戻らへんらしい。これは大変やと、すぐに松本に帰りましたが、猿田さんは3日後に亡くなってしまいました。
『マリアさま』の光
教会でお葬式をして、猿田さんの奥さんから「いしいさんには本を持っていてほしい」と、あの分厚い聖書を預かって。その後、三崎のまるいち魚店へ行きました。それで、おかみさんの美智代さんに、猿田さんが亡くなってしまったことを話したんです。
そうしたら美智代さんが「しんじさん、ちょっと待ってて。見てほしいものがあるの」と、家から大判のカラー写真と手紙が入った封筒を取ってきて、見せてくれました。
写真には、僕の家や、近所のぶどう畑、中央アルプスの山が写っていました。手紙は猿田さんがおかみさんに宛てたもので、こんなふうに書いてありました。
「まるいちの皆さんへ、美智代さんへ。いしいしんじさんを、三崎から松本にとってしまってごめんなさい。でも僕がこうして、この二人がずっと幸せでいられるように傍で見守っていますから、安心してください。彼ら二人にはそのうち子どももできて、きっと笑顔で三崎に帰ります。だから、その時を楽しみに待っていてください」
まるいちで鯖を買って帰って、その晩、鯖寿司にして神棚に供えました。「猿田さん、キリスト教の作法じゃなくてごめんな」って謝りながら。
最初にね、「(担当編集の)熊谷さんが『マリアさま』と言ったから」と言いましたけど、この本が『マリアさま』という名前になったのには、僕の人生に猿田さんがいたからということも大きく影響していると思うんです。
もし読んでくださった人たちが『マリアさま』の中に光を感じたとしたら、その中にはたぶん、猿田さんが写真を撮った時の太陽の光も入っているはずです。
猿田さんだけじゃなくて、他者に自分の光を注いで、その照り返しを受けて笑っているような、そういう人たちばかりに囲まれて僕は生きています。ほんまに、ありがたいことです。
大切な人が亡くなるのは残念やし、悲しいことですけど、それは“悪いこと”ではない。大切な人の死は、乗り越えたり、薄れたりするものじゃない。その悲しさを大事に持ったままずうっと生きて、時々誰かとそれを共有する。
僕にとって「生と死」とはそういうものです。『マリアさま』も、そんな本になったと思います。
![]()
SP盤の愛好家であるいしいしんじさん。『マリアさま』には、そんないしいさんが自身のコレクションから27篇一つひとつに1曲ずつ選んでつくったサウンドトラックがあります。
「こういう内容の話やからこの曲にしよう、ではなくて、その話を読んでいる時と同じように感覚器を震わせる曲はどれやろう、そういうふうに選びました」
「SP盤は、それが録音されたその日の、そのスタジオの空気が、じかに盤上に刻まれているという点でLP盤とはまったく異なります。その場の空気をそのまま録っている、つまり“音の版画”です。蓄音機で再生すると、空気がその時と同じに震えるんです。何年前のものだろうが関係なく、演奏者がもう亡くなっていたって、すぐそこに生みだすことができる。『マリアさま』にぴったりでしょう」
- マリアさま
- 著者:いしいしんじ
- 発売日:2019年09月
- 発行所:リトル・モア
- 価格:1,650円(税込)
- ISBNコード:9784898155103
〉プレイリストはこちらから
http://www.littlemore.co.jp/maria-sama/
![]()







































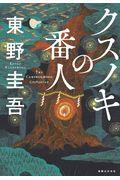
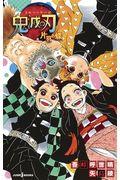























 のシンデレラ~綺麗なお姉さんはケダモノ王子様でした~
のシンデレラ~綺麗なお姉さんはケダモノ王子様でした~

















 が可愛すぎて困る!(2)
が可愛すぎて困る!(2)







































































